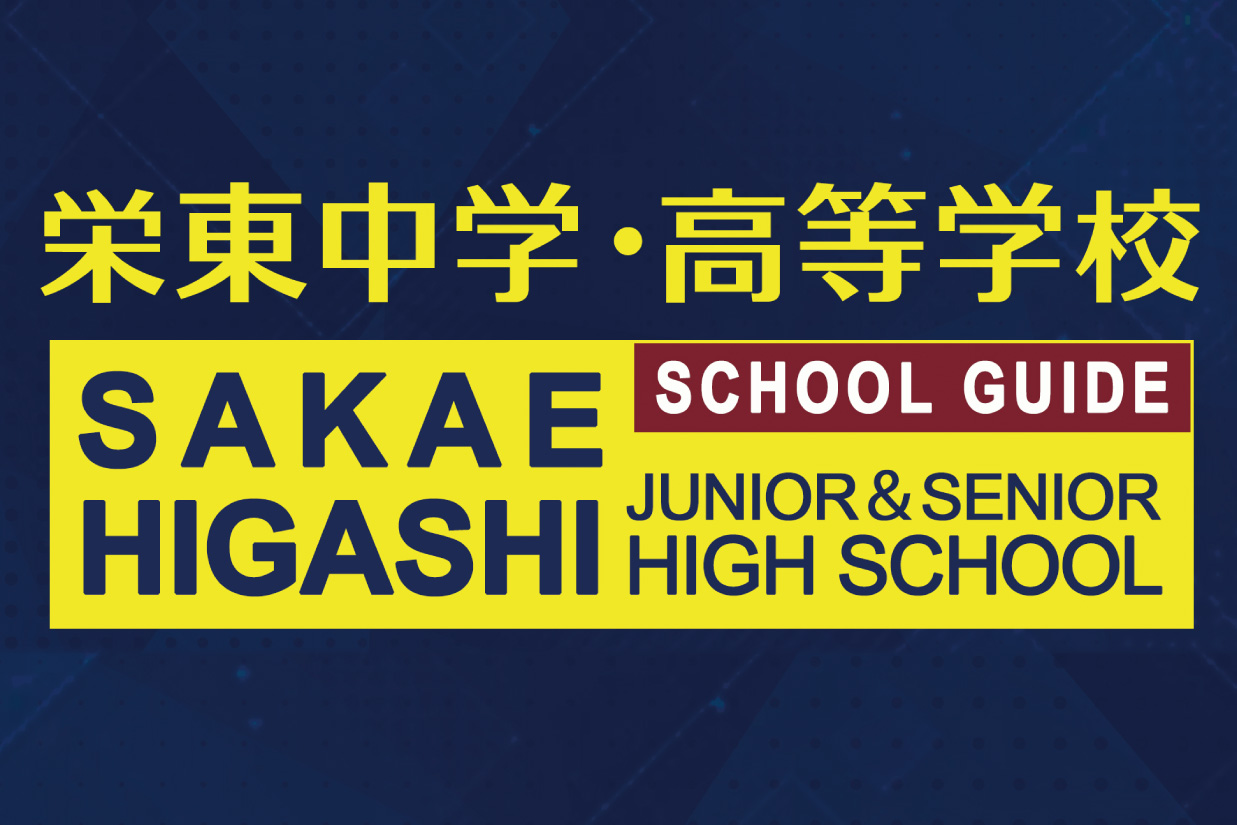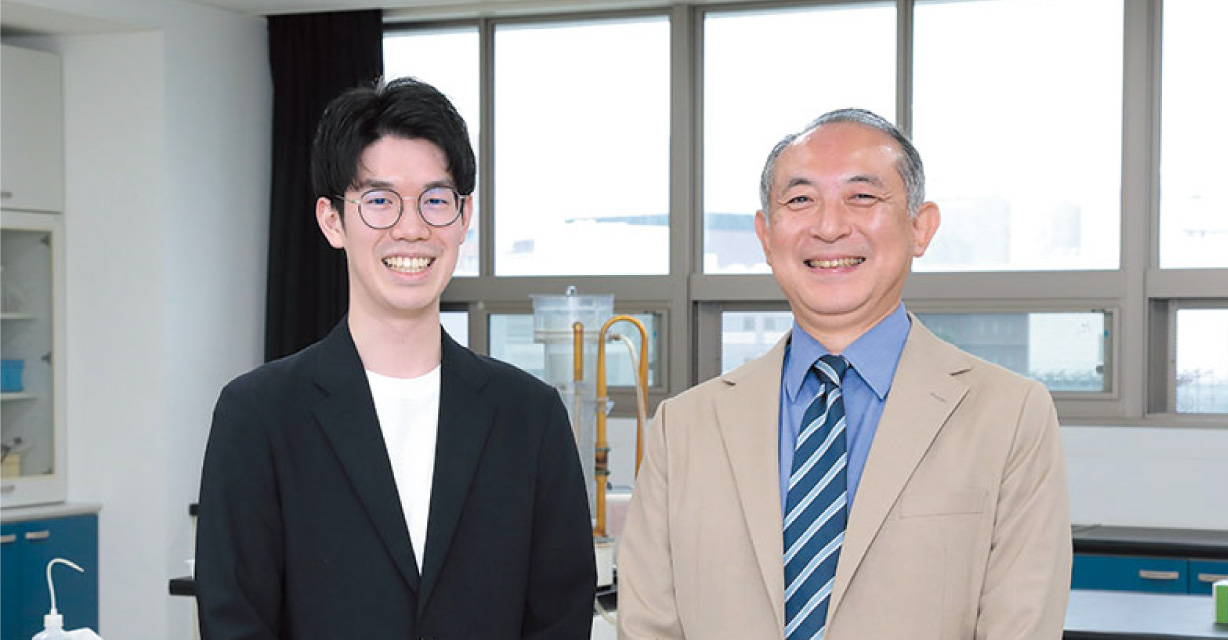左:SAPIX YOZEMI GROUP 共同代表
髙宮 敏郎 氏
右:武蔵高等学校中学校 校長
杉山 剛士 氏
100年掲げる「三理想」「自ら調べ自ら考える」力はAIの時代にひときわ輝く
髙宮 この十数年、グローバル化の進展と人工知能の発達などにより、世界は劇的に変化しています。動きの激しい時代にあって、中学・高校の教育はどうあるべきでしょうか。貴校のような伝統校では今どんな教育に取り組んでいるのか、ぜひお聞かせ下さい
杉山 1922年創立の武蔵には100年以上の歴史があります。建学の理念として掲げる「三理想」は、「東西文化融合」「世界雄飛」「自調自考」から成り、これまで脈々と受け継がれてきました。今なお色あせない三理想を大切にしつつも、一方では時代の変化を見据えて変えていくべきことがあると考えています。
創立100周年を機に、「新生武蔵」と題した新たなグランドデザインも描きました。次の100年に踏み出すために、武蔵の良さを大切にしながらさらなる進化を目指すもので、育てたい人物像として「独創的で柔軟な真のリーダーとして、世界をつなげて活躍できる人物」を掲げています。
髙宮 変化の時代だからこそ、伝統校が大切にしてきた価値がもう一度見直されるべきではないかと感じることが増えました。
杉山 三理想の根幹にあるのは、自ら調べ自ら考える「自調自考」の姿勢です。時代が変わってもその大切さは変わりません。むしろますます重要になっていると思っています。

SAPIX YOZEMI GROUP 共同代表
(代々木ゼミナール副理事長)
髙宮 敏郎 氏
髙宮 情報技術の進化は目覚ましいものがあります。人工知能が東大合格を目指す「東ロボくん」プロジェクトで知られる数学者の新井紀子先生が、AIの進出によってホワイトカラーの仕事の半分がなくなるかもしれないと指摘したのは2010年でした。それから15年がたち、AIは東大に合格できる力を持ちました。
アメリカでは生成AIによる業務の効率化で、大手企業が従業員を削減しています。今の日本は人手不足で失業率も低い状況が続いていますが、単純な仕事に従事する人が必要とされなくなる時代はすぐそこまで来ていると思います。
杉山 AIによってアメリカではホワイトカラーが減り、日本でも人口減少が進む中で労働生産性を上げるためにAIが入ってきています。武蔵の卒業生で先日講演に来てくれた黒﨑賢一さんは経理AIエージェント「TOKIUM(トキウム)」を立ち上げて活躍している人です。企業の経理部門や総務部門が回してきた事務作業をAIが担うことで時を生み、次のイノベーションにつなげていくビジネスを軌道に乗せました。彼の話を聞いて、日本のAIもここまで進んでいるのかと改めて実感しました。
髙宮 確かに経理も総務もホワイトカラーの仕事です。
杉山 同じく武蔵の卒業生で、日本の生成AIの第一人者といわれる京都橘大学教授の松原仁さんも、講演でこう話してくれました。生成AIの進化は止められないからどういうルールを作るかが大事で、AIの時代だからこそ自ら調べ自ら考えることがますます大切になる、と。情報があふれる中、単に情報を集めて整理するだけではなく、真実を見抜きながら自分なりのオリジナリティーやひらめきを加えるには、やはり自調自考が大事なのです。
「AIは責任を取らない」原理・原則を学ぶときは自分の手を動かして

武蔵高等学校中学校 校長
杉山 剛士 氏
髙宮 自調自考がますます重要な時代になっているのは明らかです。さらに今は自調自考の前に、なぜそうなるのかと問いを立てる力が大事になっているのではないでしょうか。
杉山 私たち教育関係者は問いを立てることの重要性をずっと指摘してきました。そうした力は今後ますます必要になるでしょう。松原さんは「AIは責任を取らない」と本質的な指摘をされましたが、私も自調自考の次にあるのは「自動自責」ではないかと考えています。自ら調べて考えるところで終わっていては駄目で、考えた後に自ら発言して動き、それによって生まれる周囲のリアクションを、責任を持って受け入れるという意味です。今の日本は特に自責の部分が弱いと感じます。まずかった、失敗したと思えば、責任を持ってきちんと謝ればいい。そういう思いを持つことが重要です。
髙宮 なるほど、AIは責任を取ってくれませんから。大学の先生方にお話を聞くと、多くの論文を要約させてポイントをつかんだり、日本語の論文を英語に訳させたりと、すでに生成AIはなくてはならないものになっているそうです。ただ、そうした方々は自分の中に一定の軸があるので、AIが出してきたものに対して自ら判断できる。一方で中高生がAIに頼りきってしまうと、何が本当かという判断ができなかったり、書く力が落ちたりするのではないかと危惧しています。
杉山 AIは便利なので、経験値を積んだ人が使うのは非常にいいことだと思います。学校教育の場でも特に語学学習と親和性があり、英作文の添削などは的確で早く、スピーキングも発音をうまく矯正してくれます。ただ、自分の軸ができる前の中高生が原理・原則を学ぶツールではありません。
髙宮 やはりAIを活用するには使う側に軸が求められますね。
杉山 「新生武蔵」の一つの柱として、アナログとデジタルの融合を掲げていますが、原理・原則を学ぶには手を動かすことが大事。そこにツールとしてのデジタルをうまく融合させる必要があるのです。たとえば、理科の実験は今もアナログ重視です。手作業でデータを取り、自分で方眼紙に書き込んでいくことにこだわっています。実験や自然との触れ合い、体験学習、高大連携講座など、武蔵では机上の学習だけでなく、本物に触れる体験を通して感性を磨き視野を広げる「本物教育」を重視してきました。これもまたAIの時代には不可欠なものと考えています。
高次思考力の土台には「読み・書き・そろばん」学びの根幹は変わらない
髙宮 生成AIは東大の入試問題を解けるようになりました。最難関の理三にも合格できるといわれています。では、東大受験のための勉強は不要になったかというと、そうではないはずです。人間の思考力を高めるステップとして勉強は当然必要です。生成AIで何でもできるから、これまでの教育を変えなくてはいけないという議論がありますが、AIができるから人はやらなくていいということにはならない。発達段階に合わせて思考力を高めていく教育が重要であることはこれからも変わりませんね。
杉山 高次の思考力のベースにある「読み・書き・そろばん」は、今や生成AIのほうが速く正確かもしれません。だからといって子どもたちの学びからそれらを排除するわけにはいかない。読み・書き・そろばんはすべての基盤で、それらを踏まえた思考力が重要なのですから。
実は今、数学の授業でデジタルソフトを実験的に使っています。数式が画面にすらすら出てくるので、デジタルがいいと言う生徒もいますが、鉛筆で書いて覚えるほうがいいこともあります。要はデジタルとアナログの両方をうまく使いこなすことが大事なのです。
髙宮 手で書いてみて初めて気づきが生まれることはよくあります。私が卒業した慶應義塾普通部には、フィールドノートという理科の観察ノートがありました。見て、観察して、手を動かして書き残す作業は面倒でしたが、今となっては当時の教えに感謝しています。最近、物事をゆっくり見る「スロー・ルッキング」という言葉が注目されているように、よく見る、よく観察することの大切さは、むしろ社会に出て仕事をするようになってから痛感しています。
杉山 手で書く感覚はとても大事です。書いているうちにいろいろな物事が俯瞰で見えてきて、気づきが生まれる。見ることはすべての根幹で、私たちは見ることによって物事を分類しています。それがデジタルに置き換わると、自分で分類する作業ができなくなります。改めてわれわれが考えていかなくてはならない課題だと思います。
世界へ飛び出す体験を日本人の強みを生かし西洋スタイルも身につける
髙宮 昔に比べて今はあらゆることで選択肢が増え、各自がその都度判断しなければならない局面が増えています。何を学んでどう成長するか。子どもたちは自分で調べ考えて、自分の道を決めて動いていかなくてならない時代なのかもしれません。「本物教育」という意味では、海外留学などのグローバル体験も将来を考えるきっかけになるのではないでしょうか。
杉山 三理想の一つに「世界雄飛」があります。武蔵生にはどんどん外へ出てグローバルな体験をしてほしいので、提携校での海外研修や留学生との交流、英語で科学を学ぶイマージョンプログラムなどさまざまな機会を設けています。「新生武蔵」のグローバル構想でも、生徒たちには単に世界へ飛び出すだけでなく、世界をつなぐグローバルリーダーに育ってほしいとうたっています。
髙宮 海外研修に参加した生徒はどこか変わりますか。
杉山 確実に成長して帰ってきます。だから思い切って外へ飛び出し、どんどん進んでいってほしいです。三理想の「東西文化融合」という観点からも、今こそ日本の強みや課題を捉え直し、私たちはどういう役割を果たすべきかを考える必要があると感じます。
髙宮 今アジアで起こっていることで言うと、中国の大学入試統一テストの出願者は約1335万人で、日本の大学入試共通テストの出願者約50万人の26倍超に達しています。また、中国の16〜24歳の失業率は23年6月に2割を超えました。こうしたことを背景に、中国から来日する若い世代はかなりの人数に上っています。日本の若者はいずれ彼らと労働市場でぶつかることになるでしょう。
方、年間の出生数が2000万人といわれるインドでは、大卒以上の失業率が3割近くになっているようです。上昇志向の強いインドの若者たちは今アメリカに渡っていますが、日本の若者は彼らと勝負できるでしょうか。日本人が世界で生きていくためには、世界的に信頼されている日本の倫理観や正義心といった美点を生かしていくことが必要です。
杉山 人間教育を含む日本の教育に期待して、中国から日本の学校に入学する生徒が増えています。日本人の勤勉さや我慢強さ、誠実さは世界に誇るべきものでしょう。武蔵の卒業生でJICA(国際協力機構)やコンサルのマッキンゼー、世界銀行を経て、現在はスイスに本拠を置くグローバルファンドの保健システム部長を務める馬渕俊介さんは、日本人が世界のリーダーになり得るポテンシャルについて講演会で語ってくれました。彼は、日本人の強みは緻密に計画できる力や相手の感情に寄り添って意思決定を促す力にあり、これは日本で生活しているとおのずと身につくものだと言います。ただし、日本人が世界で活躍するには明確にビジョンを示し、自己主張や議論ができる欧米スタイルを持つことが重要だと話してくれました。
髙宮 日本人が世界から得ている信頼をいかに生かすかですね。
杉山 日本のスタイルを持ちながら西洋スタイルも身につける。両方をうまく使い分けることが大事なのでしょう。馬渕さんは武蔵生に「自分で創り 自分で切り拓く 自分の人生を生きよう」というメッセージを残してくれました。多様な分野で新しい時代をつくっていく卒業生たちもそうですが、今の武蔵生を見ていても日本にはまだまだ大きな可能性があると感じます。
とがっていても柔軟であれ
仲間とともに学び
一緒に成長する6年間を

自然豊かで落ちついた武蔵学園のキャンパス
髙宮 在校生にとって、さまざまな分野で活躍する卒業生の皆さんに学ぶところは大きいですね。
杉山 松原さんと馬渕さんは「自調自考」が大切で、黒﨑さんはたとえ成績が悪くても武蔵では否定されなかったことが今につながっていると話してくれました。自由に学び、好きなことにどれだけ打ち込めるか。アメリカのピッツバーグ大学で発生生物学の最前線に立つ石原圭祐さんやMetaのソフトウエアエンジニアとして活躍する川邉雄介さんなど、最近の講演会に登壇してくれた方々も口をそろえて同じようなことを言います。
髙宮 自由に伸び伸びと学び、好きなことを見つけて夢中になる。充実した中高時代が世界で活躍する土台になっているようですね。
杉山 「新生武蔵」では独創的で柔軟というキーワードを掲げていますが、もともと武蔵には独創的でとがっている生徒が数多くいます。どんどんとがり、それでいて柔軟というところを大切にしたいです。
髙宮 単純にとがるだけでなく、いろいろなものを受け入れる柔軟性も必要ということですね。
杉山 とがっている軸と受け入れるキャパシティー。それがどこで育つかというと、中高6年間の時間と空間です。誰かに言われてやるのではなく、自調自考でさまざまなことに挑戦してほしい。ときには仲間とぶつかることもありますが、それを乗り越え、さらに外へ飛び出すことによっていろいろな発見をしてほしい。
高3生に武蔵での学校生活を振り返ってもらうと、「いろんなことを好きにやらせてくれた」「自調自考の精神が身についた」「仲間との関係が大変だったけど、うまく乗り越える力がついた」といった答えが返ってきます。授業で身につく学力だけでなく、授業以外の時間・空間で得られるものは非常に大きいです。
髙宮 同じキャンパスで仲間と一緒に学ぶことが大事です。今、高校生の1割が通信制の学校に通っていて、今後その割合は増えるといわれています。通信制ならではのメリットもありますが、実際に学校に通い、仲間とのぶつかり合いも含めて成長していくことは貴重な経験になると思います。
杉山 その時間・空間こそが大事です。そこで初めて自調自考の精神が生まれると考えます。
髙宮 同じ学校で一緒に過ごした仲間との信頼関係は、卒業して何十年たっても変わりません。時間と空間を何年間か共有したからこそ、卒業後にたとえ頻繁に会わなくてもずっとつながっている安心感を持てます。
杉山 その一方で、学校は限られた空間なので、グローバルな視野を持つためには思い切り外に飛び出していくことが求められます。両方が必要なのです。
髙宮 仲間とともに学ぶこと、外へ出て新しい世界を知ること。どちらも大事ですね。

中央を横切るように流れる濯川
杉山 もう一つ生徒に伝えているのは、人として大切にすべき人権感覚を持ってほしいということです。公共心も同様です。自分のことだけではなく、みんなの幸せとは何だろうということを少しずつ考えてほしい。人権感覚、あるいは公共心は意識的に伝えていく必要があるものと考えています。
髙宮 貴校が育てたい人物像がよくわかります。最後にお聞きします。これから中学・高校へ進む子どもたちにどんな小学校時代を過ごしてほしいとお考えですか。
杉山 好奇心と向上心を大事にしてほしいです。何かを面白がったり、伸びようとしたりする気持ちを大切にしてほしい。好奇心や向上心は子どもならみんな持っているので、保護者の皆さんはそれをつぶさないでほしい。先ほど述べた公共心ともつながりますが、社会でのマナーも小学生のうちに身につけてほしいと思っています。
※本記事は『日経ビジネス 教育特集号 AUTUMN.2025〈東京ストーリー〉(日経BP社)』に掲載されたものです。