※本記事は『日経ビジネス 教育特集号 AUTUMN.2025〈東京ストーリー〉(日経BP社)』に掲載されたものです。
今年で創立140周年を迎えた成城中学校・高等学校。臨海学校と林間学校を日本で最初に導入するなど男子校としての長い伝統を誇り、多彩な領域で活躍する人材を多数輩出している。今回登場する手島涼太さんも、中学時代からハイドロゲルの研究に打ち込み、現在も研究者として同じテーマを追い続けている。中高時代の思い出や現在の研究などについて、当時の恩師・水野和浩先生と語り合ってもらった。お二人のお話から見えてくるのは、同校ならではの教育風土や指導法の特色だ。
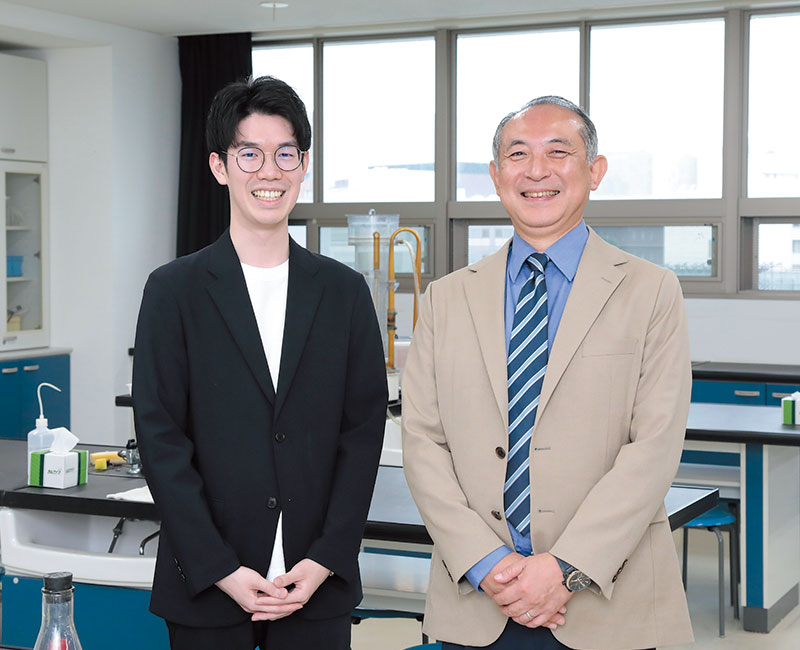
左:ライオン株式会社 研究開発本部 名古屋市立大学大学院
薬学研究科 研究員 手島 涼太 さん
右:成城中学校・成城高等学校 学年主任・理科教諭
水野 和浩 先生
水野 手島くんは、現在はどのような仕事をしているのですか。
手島 ライオン株式会社で研究者として衣類用洗剤などの開発をしています。その中でも、私が携わっているのは、サステナブルな生活や自分らしい生活といった未来の生活者の価値観に訴えるような開発研究です。短期的な視点ではなく、もう少し長い目線での新規事業や技術の立ち上げに近いような業務を担っています。
水野 そうなると化学の知識だけでなく、社会経済的な動向など、幅広い視点が必要になってくるでしょうね。
手島 はい。本当にその通りで、技術的な視点だけではなく、生活者が何を求めているか、未来の生活はどのように変化するのか想像しながら研究する視点が求められます。技術的なハードルの高さや市場浸透性といったことなども視野に入れながら、チームとして取り組んでいます。
水野 一方で、大学の研究者としての顔も持っているそうですね。
手島 今年から、名古屋市立大学大学院薬学研究科の研究員も兼任しています。こちらでは成城中時代からずっと続けてきたハイドロゲルの医療応用に関する研究に取り組んでいます。豊富な臨床経験を持つ先生方からご助言をいただきながら研究を進めています。
水野 とても忙しそうですが、充実していそうですね。企業での研究と大学での研究には、何か違いは感じますか。
手島 企業での研究は、社会的なニーズと技術的なシーズがマッチした時に、大きな価値を発揮するものであると思います。一方で、大学での研究は学術的な新規性や貢献性も重要であると思います。同じ研究ですが、色々な視点があることが面白いですよね。

高1時に日本学生科学賞東京都大会で表彰を受ける(左:手島さん 右:水野先生)
水野 最初に手島くんが私のところに来たのは中学3年生の夏休み前くらいでしたか、「日本学生科学賞」という研究論文のコンクールに応募したいといって、自分でやったゲルビーズに関する研究を持ってきましたね。人工イクラなどにも応用されるゲルビーズは、アルギン酸と塩化カルシウムを反応させて作るハイドロゲル膜ですが、その膜の硬さと反応時間に比例関係があると言い出して…。でもデータもないのに比例関係があるとは言えないよねという話をして、データをとるために学校にある器具で実験してみたら…といったようなアドバイスをしたのが発端だったかな。
手島 はい。当時私は吹奏楽部に所属していたので空いている金曜日を使って実験を繰り返しました。水野先生の厳しいご指導のおかげで(笑)、優秀賞を受賞することができました。
水野 私は大したことはしていなかったと思いますよ。ただ、アドバイスを求められたときには、答えられる範囲で助言を行い、基本的には手島くんの主体性に期待して、見守っていましたね。
手島 そのようにしていただいたことが功を奏したのだと思います。まだ学校では、アクティブラーニングという言葉が浸透する前で、一方通行型の授業が多かったです。そんな中、自分で考えて実験して、結果について先生とディスカッションして…という主体的な学びを経験できたことが、現在の土台になっていることは間違いありません。
水野 そもそもなぜ人工イクラに興味を持ったのですか。
手島 小学生の頃から理科に興味があり、中学2年生の頃に化学と生物が好きになりました。ちょうどその頃、研究者にあこがれを抱き、東京理科大学のある先生に「研究室を見学させていただけませんか」といきなりメールを送りました。すると、快く受け入れてくださり、その研究室で紹介されたのがハイドロゲルの研究でした。その後私は、東京理科大学に進学し、その研究室で研究生活を過ごしました。
水野 研究者へのあこがれはよくわかります。私が高校生のときに利根川進氏がノーベル生理学・医学賞を受賞したんです。理学系の化学系学科で研究者を目指したいと思いました。ただ研究者になっている教え子は何人もいますが、中学時代から自分で研究テーマを考えて…という生徒は手島くんの他にはいませんでしたね。
手島 日本学生科学賞への応募が大きなモチベーションになっていたのは確かで、高校2年生までは毎年応募して、何らかの賞をいただいていました。何ヶ月も同じ曲を練習する吹奏楽部での経験も、研究に向き合う姿勢を形作ってくれたと思っており、その意味で成城での生活は私の原点になっています。
水野 その後、大学でもハイドロゲルの研究を続けたわけですね。
手島 はい。中高でこの研究は終わると思いきや、大学でも続けたくなって。大学1年生の冬に学会に飛び込みで参加して、そこでたまたま出会った理科大の薬学部の先生に「先生の研究室で研究をさせていただけませんか」と直談判しました。さまざまな先生方との出会いに恵まれて、大学院まで同じ研究テーマを追求し、学会で賞をいただくこともできました。
水野 手島くんらしい積極性が活きていますね。大学の研究者になるということは考えなかったのですか。
手島 当初はそのつもりでした。転機は、大学院生の頃に参加した学会でした。私が研究を発表した際に、とても熱心に質問してくださる企業研究者がいて、その方が、ライオンの研究者でした。こんな研究者がいる企業で働いてみたいと思い、この道を選んだ経緯があります。

校舎には生徒のやりたいことを実現できる
施設・設備が整っている
水野 そのような経緯があったのですね。さまざまな人や機会との出会いに恵まれたように思います。そんな手島くんに、改めて成城の魅力について聞いてみましょうか。
手島 水野先生のように、先生方が生徒の主体性をうまく引き出し、親身に応援してくれるという校風があることはやはり大きな魅力だと思います。6年間、自分らしく自然体で過ごすことができたと思っています。学習に限らず、臨海学校や林間学校など、様々なプログラムがあることも成城の良いところだと思います。
水野 最後に、成城の後輩たちに何かメッセージをお願いできますか。
手島 大学時代の恩師から頂いた言葉ですが、「大胆さと緻密さを併せ持て」という言葉を贈りたいです。社会に大きな影響を与える革新とは、「大胆な発想の上に、緻密な検証を重ねたものである」という意味です。社会人となった今、この言葉は身に沁みて実感しています。ぜひ後輩の皆さんと一緒に精進していきたいと思っています。
成城中学校・成城高等学校 お問い合わせ先
TEL.03-3341-6141
> 学校ホームページはこちら※本記事は『日経ビジネス 教育特集号 AUTUMN.2025〈東京ストーリー〉(日経BP社)』に掲載されたものです。