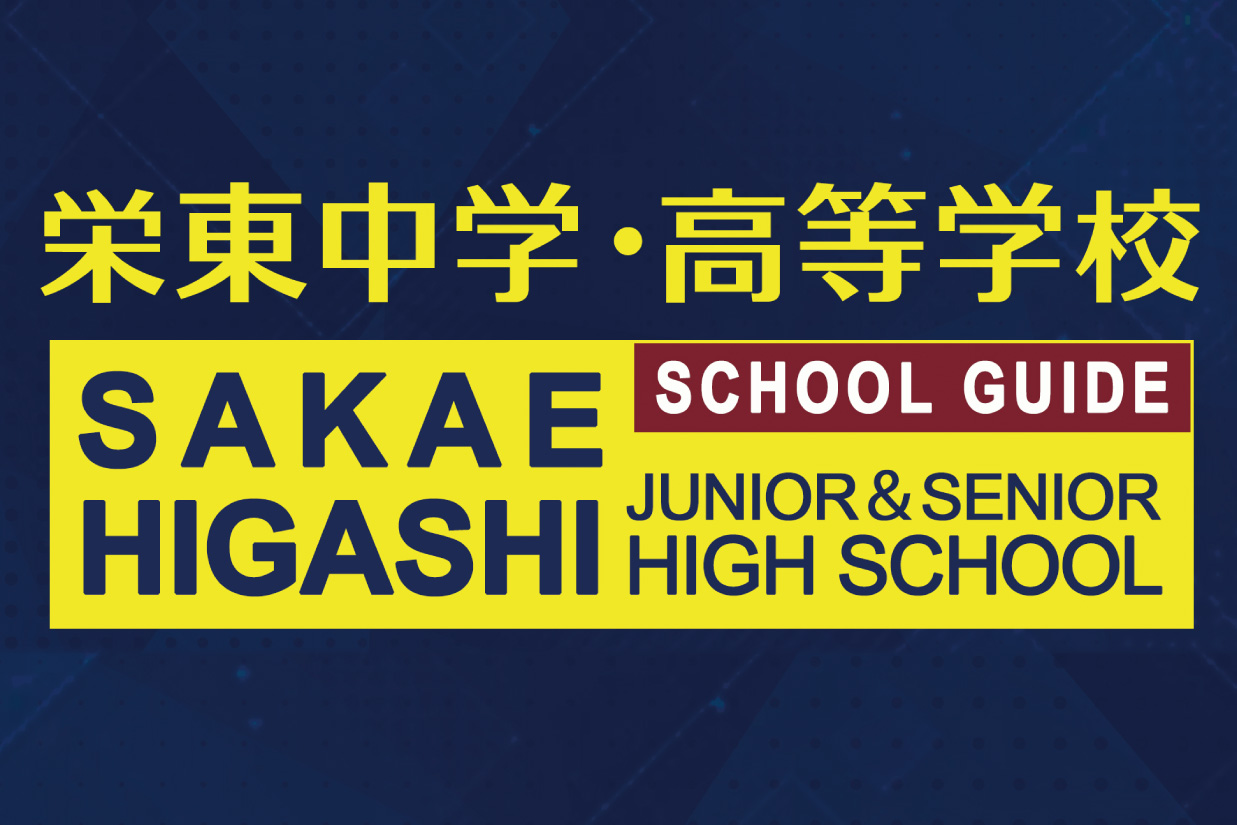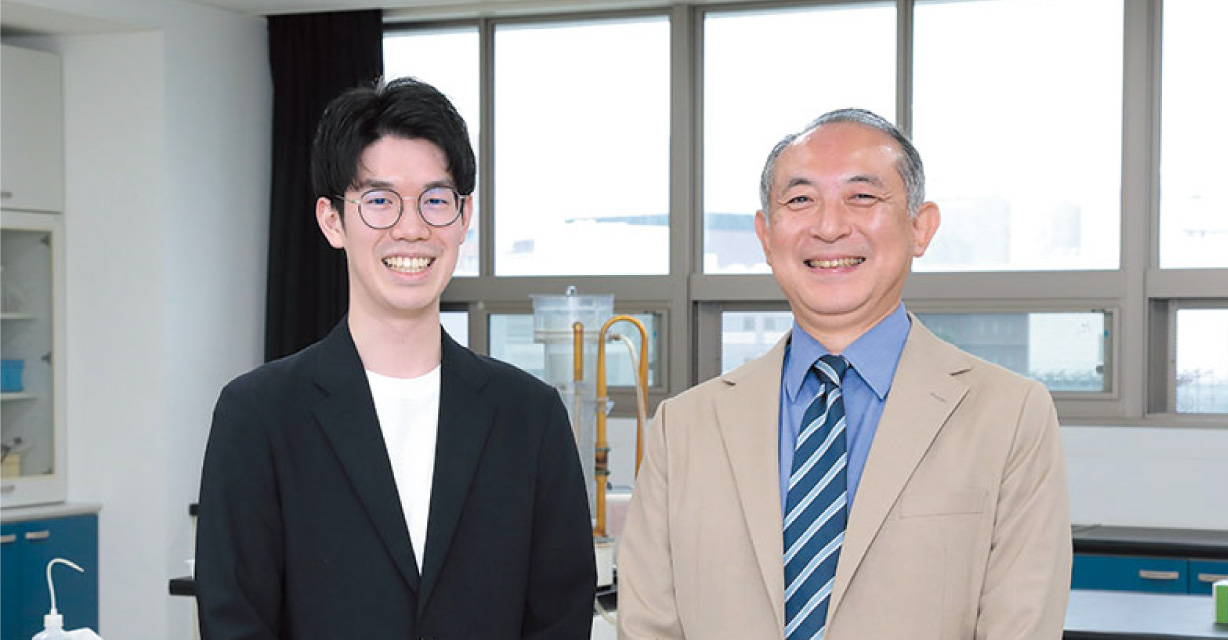※本記事は『日経ビジネス 教育特集号 AUTUMN.2025〈東京ストーリー〉(日経BP社)』に掲載されたものです。
恵泉女学園中学・高等学校
キリスト教に根ざした
人格教育で平和を
実現する国際人を育成
2029年に創立100周年を迎える恵泉女学園中学・高等学校は、伝統ある女子校ながら、TPOに合わせた自由服や、個性を尊重するのびのびとした教育環境をもつ。その一方で、早期からSTEAMやICTなど先進的な教育を行い、高い学力と知的探究心を培っている。その土台には、常に「聖書」「国際」「園芸」という創立以来の教育基盤がある。平和への不屈の意志とともに、その実行力を育む教育について、本山早苗校長と松井信行副校長に話を聞いた。

左:副校長 松井 信行 先生
右:校長 本山 早苗 先生
命の尊さに触れる「園芸」で
鍛えられる多様な非認知能力
キリスト教に基づく教育を行う恵泉女学園は、キリスト教徒として平和を尊ぶ河井道によって設立された。世界が戦争へと向かいつつあった1929年、「世界平和の実現には少女からの教育が必要だ」と考え、自宅を学び舎に開放したのが始まりである。
以来、同校は「聖書」「国際」「園芸」を教育基盤に主体性・多様性・協働性を育んできた。本山校長は「聖書の『自分を大切にしなさい』という教えを基点に、『自分と同じように隣人を大切にしなさい』という教えが『国際』につながり、『命をいただいて生かされている』という教えが『園芸』につながっています」と話す。
「園芸は、命の尊さを知り、感謝する心を養うことを目的にしていますが、友達との協働や作業の段取りなどを経て、現代において社会性やコミュニケーション能力などを指す「非認知能力」も育成しています」とは松井副校長だ。

伝統ある英語スピーチコンテスト。中3~高2の生徒を前に、毎年ハイレベルな発表が繰り広げられる
『国際』の土台となる英語教育では、発信力を鍛えながら、多彩な国際理解教育プログラムで世界と交流する。海外からの留学生と共に英語漬けの5日間を過ごす「グローバル・スタディーズ・プログラム」には中3から高2まで参加できるが、参加した生徒たちにとって、その後の英語学習や留学へのモチベーションになっている。従来のオーストラリアやカナダへの短期から長期の留学プログラムに加え、3年前からはシンガポール訪問プログラムを実施し、成長するアジア圏での学びにも目を向けている。
さらに、海外からの受け入れにも積極的だ。
「ホームステイは受け入れ先を見つけるのが難しいと言われますが、本校ではすぐに枠が埋まります。海外に友達ができるってこんなに楽しいんだという経験が、国際人としてのスタートになります」(本山校長)
伝統の人格教育を土台にしながら
科学的思考力で生徒の可能性を広げる
こうしたカリキュラムの根幹を成すのが、毎朝の礼拝だ。とりわけ、礼拝で行われる「感話」は、恵泉生の礎となる。
「自由なテーマでみんなの前で話をします。一見、話をすることに意味があるようですが、実は人の話を黙って傾聴することにも意味があります。ふだんの生活では、聞きたくない話は聞かないという選択もできます。しかし、感話は反論があっても最後まで黙って耳を傾けなければなりません。そのことが自分との違いを知るきっかけになります」(松井副校長)
恵泉女学園の底力はそれだけではない。こうした創立以来の人格教育の上に、さらにしっかりとした知的探究心を育んでいる。その要となるのが、中3から参加できる「サイエンスアドベンチャー」だ。分野別の班で研究活動を行い、大学訪問や外部の研究発表会などにも参加し、発信力をも磨く。中3理科での「探究実験」も然り。科学的な思考力を身に着け、医学部をはじめとする理系への進路開拓にもつながっている。あえてコース制をとらず、多様な考えを持つ生徒が同じ環境で学ぶ科目選択制もまた、生徒の可能性をどこまでも伸ばすしかけとなっているのだろう。
「河井先生は、自分ができることに誠実に取りくむことを大事にされたと思います。その精神は今も受け継がれているものの一つです」と本山校長は語ってくれた。
安田教育研究所・安田理先生の
女子伝統校の
ここが魅力
先ごろ社会派小説『BUTTER』でイギリスの権威ある文学賞を受賞した柚木麻子さんは恵泉の卒業生。恵泉の創立者河井道の半生を描いた『らんたん』という作品がある。その中に恵泉が育てようとしている人間像がある。「危険や不安があっても決して動ぜず、新しい世界に飛び出す勇気がなければ、一番大切なものに出会えない」。恵泉はどこよりもその勇気を生徒に与えてくれる学園だと思うのだ。

安田教育研究所
代表 安田 理 氏
恵泉女学園中学・高等学校 お問い合わせ先
TEL.03-3303-2115
> 学校ホームページはこちら